人文学部1年の高橋遼平です。本ブログでは、新潟大学1年次の教職課程についてご紹介します。本ブログをお読みの方は教職にご興味をお持ちかと思います。私自身も現在、教員を目指して教職科目を履修し、学業に励んでいるところです。本ブログをお読みになった後、教職について少しでも知識と興味を深めていただけたらと思います。
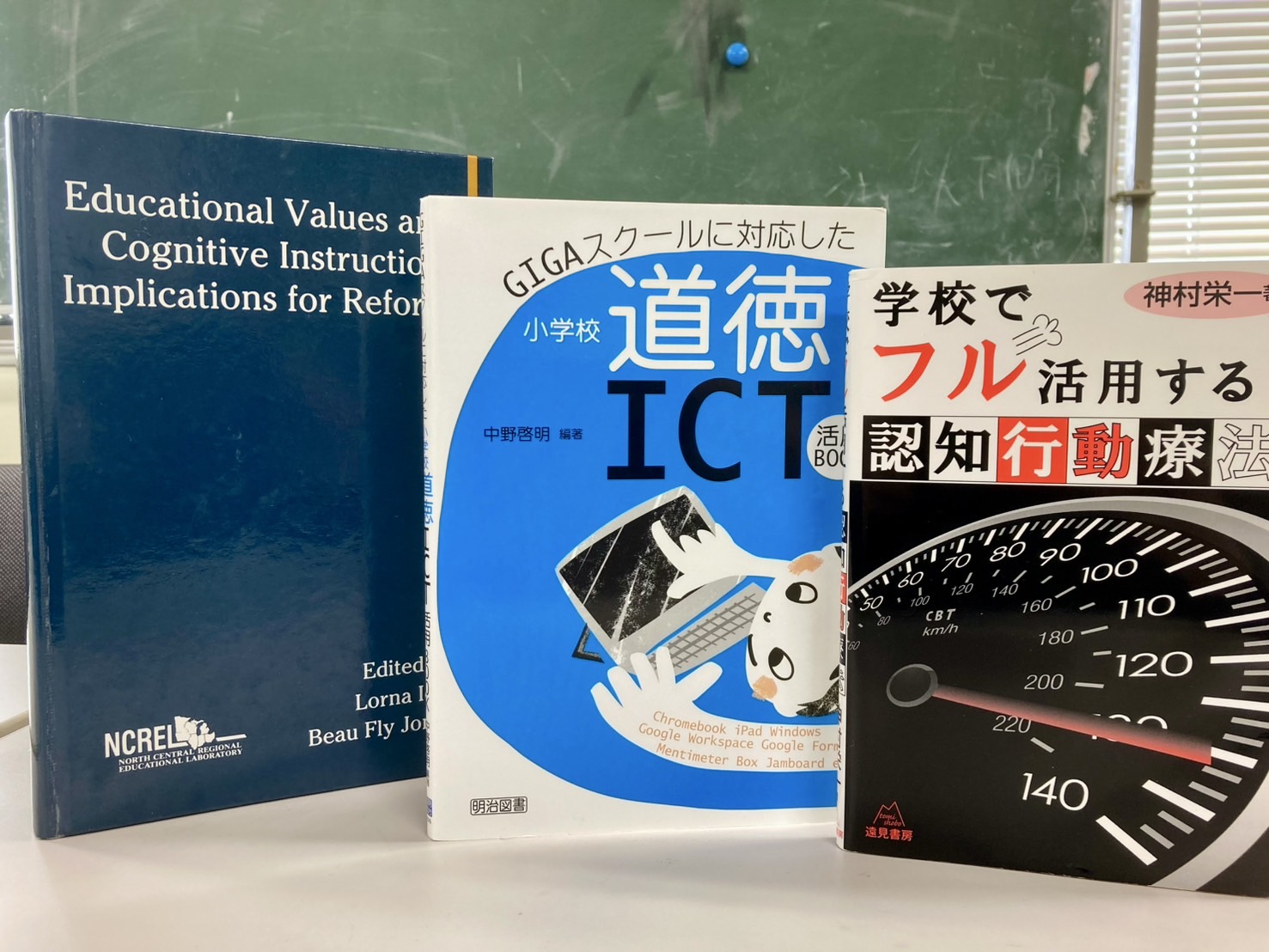
記事の目次
教職入門~教職の課題の理解
教職入門は、第一学期に履修しなければならない教職科目です。本講義は、主に教職の意義および教師の役割・職務内容について学習し、教職の課題の理解と取り巻く現状ついて考えるといったものでした。その当時の社会風潮、またそれに関連する法整備によって昔と今の教職の意義・役割には大きく違うところがあります。
一方で、特別給与法を始めとする法律、教師の仕事を超えた作業の増加などまだまだ課題があることを学びました。そのような課題や法改正についてグループワークで意見交換をし、自分と相手の双方の考えを深められるのがこの講義の魅力ではないかと思います。
教育・学校心理学B~学習の仕組みから人間関係の在り方まで
この講義は、第二学期に履修しなければならない教職科目です。本講義では、教育に関連する学習成立の仕組み、学習指導法、人間関係・環境の在り方などを心理学的理論の観点から学ぶものです。心理学と聞いて難しそうだと思いましたか?私にとっては大変興味深い講義です!
例えば、1~9までの数字が1桁から10桁まで羅列されており、それぞれ1桁から順に数字を読み、その後すぐに紙に書くという実験をしてみましょう。さあ、心理学的には何桁まで紙に書けるでしょうか?
正解は、7桁±2までと言われています。実は、人間の短期記憶の限界はこの量なのです。少ないと思いましたか?多いと思いましたか?私は、意外と多いなあと感じました!
また、学習と心にはどのような関係があると思いますか?教師と生徒との関係づくりで大事なことはどんなことだと思いますか?そんな疑問を教育と心理学の関係から学習しています。
データサイエンス総論Ⅰ・Ⅱ~データから問題解決に必要な知見を引き出す
この講義は、データサイエンスという統計学や情報工学などを用いてデータから問題解決に必要な知見を引き出す研究分野について学習します。Ⅰでは、データサイエンスにまつわるデータの種類や分析方法など基礎の基礎を学びました。
現在進行形で学んでいるⅡでは、Ⅰで学んだこと基に実際にPythonというプログラミング言語を使用してデータ分析を行っています。つまり、Ⅰの応用講義ですね。
コンピューター関係に弱い私は、なんとか頑張っています。教職にかかわらず、将来、社会人となった時にたくさんのデータを扱います。そんな時にデータを分析できるというのは大きな強みです。学生時代だけでなく将来にも役に立つデータ分析を学び、同時に分析力を養うことができる講義です。
日本国憲法~事例を取り上げながら
この講義は、名前の通り日本国憲法について学びます。近年重視されているプライバシーの権利や表現の自由など教職に就くにあたっても重要なこと、そして教養として知っておかなければならない法律、事例について学びました。
本講義では教職関連の内容ではなく一般的な日本国憲法の仕組み、内容について学ぶことができ、主に教職関連の法律、事例を取り上げた教職入門と合わせて知識を深めることができました。
以上4つの教職科目についてご紹介しました。2年次からは各個人それぞれが学びたい分野に進んでいきます。私は日本語学・日本文学に興味があるため、その進路に進み、その過程で国語の教員免許を取得したいと考えています。
教職課程は大変だと言われがちですが、そんなことないと思います。だって、教員になりたいからそこに飛び込んでいるのだから。これからも精一杯学業に励んでいきたいと思います。
最後に、このブログを読んでくださった皆さんが教職について少しでも知識と興味を持っていただけたなら私もこのブログを綴ったかいがあるとともに嬉しく思うところです。