7月8日、私達は社会学を専門にする伊藤嘉高先生の研究室を訪れ、インタビューを行いました。
インタビューでは、伊藤先生の経験やその中で感じたこと考えたことなど私たちの今後にも役立つお話をたくさん聞かせていただきました。みなさんの今後にも参考になること間違いなしの記事になっております。
- 日時:2022年7月8日(金)12:55~14:25
- 場所:総合教育研究棟 F690
- インタビュアー:齋藤彩波(1年)
- インタビュイー:伊藤嘉高先生(社会文化学プログラム准教授)
- 記事制作:鎌田康希、高岡優里、田村優衣、齊藤彩波
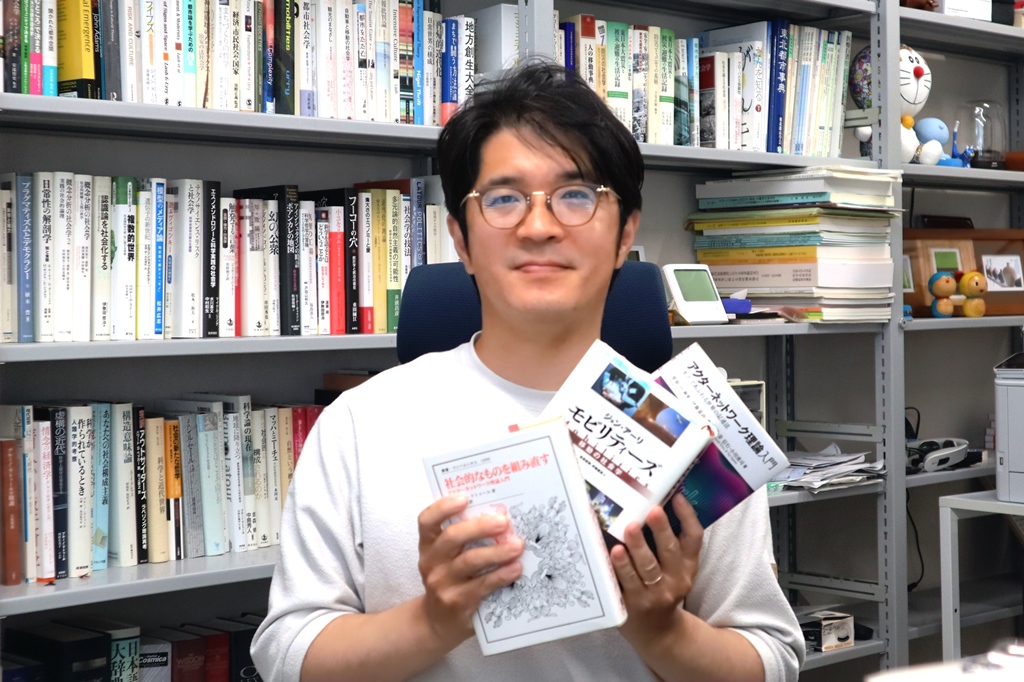
記事の目次
社会学との出会い~本屋でたまたま
学生(以下齊藤):先生のご専門は地域社会学とお伺いしていますが、社会学は国語の教科書の評論文で読むことがありました。先生はいつ頃からそういった分野に興味を持ち始めたのですか?
伊藤先生:社会学という学問に出会って、学びたいと思ったのは高校生の時です。ただ、「社会」と自分の関係について考えてみると、中学生の時までさかのぼることができるように思います。勉強を頑張る人間がバカにされる土地柄だったので、勉強中心の学校生活を頑張っても「生きている実感」がなく、つまり、「何のために生きているのか」がわからず無気力になってしまった。だから、はやく「社会」に出て、「社会」の役に立ちたいと思うようになっていました。そのせいで、中学3年の進路相談の際に「高校にはいきません」なんて言って、先生を困らせたりしていました(笑)
学生:ひぇ~ それは学校の先生も驚きですね(笑) 。でも、高校には進学されたんですよね? それはどういった心境の変化が?
伊藤先生:さすがに学校の先生や親に大反対されて、そこまでの意気地がなかったんでしょうね。でも、早く社会に出たかったので普通科の高校は嫌で、どこかみんなが納得してくれるところはないかと探してた時に高専の存在を知りました。高専の偏差値を調べてみると、まあこれなら納得してくれるだろうと。「人の評価から逃れられる」とも思って、地元にある豊田高専の環境都市工学科にいくことにしました。親には受験前日まで大反対され続けましたが(笑)
学生:えっ!!じゃあ先生はもともと理系だったんですか?
伊藤先生:そうです。ひたすらまじめに測量したり、製図したり、構造計算をしたり、土質試験をしたりしていました。でも、高専では技術者になるための勉強はできても、それが社会にとって必要なことなのか考えたり判断したりするための勉強はできなかったんです。当時は「箱もの行政」といって無駄な公共事業に対する批判もあったりして、「これでは社会の役に立てるか怪しいぞ」って悩むことになりました。
けれども、誰も導いてくれる人、モデルになる人がいなくて、どうしたらよいのかわからない。そこで、なぜか哲学の本に答えが書いてあるに違いないと思って、読んで見るのだけど、さっぱりわからない。凡人はいくら独学で頑張ろうとしても限界がある。
ただ、高専はおもしろいところで、歴史や政治経済といった文系の科目については大学の先生が教えに来るんです。4年生の哲学の授業で、ベルクソン研究者の岡部聰夫先生が教えに来てくださいました。その岡部先生が夏休みの自由課題として、ベルクソンの『物質と記憶』かプラトンの『ゴルギアス』を読んでレポートを書けという課題を出してくれたんですね。
何やらおもしろそうだったので、『物質と記憶』について自分なりに書いてみました。もちろんひどいレポートだったはずです。ところが、岡部先生は懐の広い先生で、それがきっかけで、ご自宅での読書会に招いてくださるようになりました。そこで、ゲーテやベルナール、マッハ、ジェームズ、ホワイトヘッド、プリゴジン、そしてベルクソンに至るまで「経験的な」哲学の読み方を学ぶことができました(なぜこれらの名前を挙げたかというと、私が今研究しているアクターネットワーク理論と密接につながっているからです!)。
ここからが重要なのですが、そんななか、中華料理屋で稼いだバイト代を握りしめて、哲学青年を気取って、名古屋にある一番大きな本屋にプラトン全集の最新の配本を買いに行ったんですね。そのときに何となく哲学の棚の後ろを振り返ったら、それが社会学の棚だったんです。
それまで社会学のことは何も知りませんでした。けれども、並んでいる背表紙のタイトルをみて「これは、もしや……!?」と思って、いくつかの書籍を手に取って読んでいくなかで、私が専門にすることになる地域社会学の本、正確には鳥越皓之先生の『環境社会学の理論と実践―生活環境主義の立場から』に出会い、「これだ!」と思いました。今でもはっきりと覚えています。
私は「何が社会のためになるのか」という問題の正解を探し求めていたけれども、「それを決めるのは社会の構成員である住民自身である」という当たり前の視点が自分に欠けていたことに気づかされました。でも、その気づきは「たまたまの出会い」によるものだったんです。
というわけで高専の5年生になって文転を決意したのですが、当時は、理系の高専から大学の文系学部に編入学する道はとても狭かったんですよ。でも、運よく、地元にある名古屋市立大学の人文社会学部に拾ってもらいました。「就職するんじゃなかったのか」と親にはあきれられました(笑)
大学で学ぶということ~知りたいことにのめり込む
学生:高専4年生の時に初めて社会学と出会ったんですね。3年次編入で社会学を学び始めて大変ではなかったですか?
伊藤先生:大変っていうのはなかったですよ。とくに「社会調査実習」(新大の社会学でも開講されており、社会調査士の資格取得のために必要になります!)は、自分で調査テーマを決めてチームを組んで夏休みに集中して調査ができて、すごく楽しかったです。文系の授業は、まともに試験勉強をしなくても単位が取れてしまうので幅広く学べて、知りたいことにはとことんのめり込める。それが向いていたのかもしれません。
そうそう、編入学試験では面接があって、そこでは「住民参加のまちづくりがやりたいです」と言っていたんですが、結局入ったゼミは、社会病理学の先生(石川洋明先生)のところだったんです。社会病理学はいじめやアルコール依存症などを扱う学問分野ですが、社会病理学そのものに興味があったわけではありません。入学後のゼミ説明会での石川先生の言動―「私のゼミに入ると苦労するので、勧めません」と満面の笑みを浮かべながらおっしゃっていました―に強く惹かれてしまったんです。
学生:えっ、それ大丈夫なんですか(笑)
伊藤先生:いや、大丈夫なんです。この経験から一つ皆さんにお伝えしたいのが、あまり直截的に考えてゼミとかを決める必要はない、ってことです。これから専攻とかを決めていくと思いますが、自分のやりたい学問がやれるゼミに行くっていうよりは、この先生面白そうだな、相性合うなって思えるかの方がよっぽど重要だと思います。
ほんとうにその教員の研究に興味があれば話は別ですが、ただ学びたい専門分野の先生だからという理由でその教員のゼミに入った場合、思想や考え方の違いで衝突してしまうかもしれないし、教員の経験と知識量にはかなわないので、のびのびやれなかったり依存してしまうかもしれません(もっとも、最近はハラスメントに敏感なので、そんなことは気にしなくてよいはずです!)。
逆に異なる専門分野の教員のゼミに入れば、自分の意見を純粋に「きちんと学問的な作法、論証の手続きに則っているか」という点から客観的に扱ってくれるし、そこから新たな可能性が見えてくることもあります。
ただし、このやり方には注意も必要です。基礎ができていないまま研究を進めると独りよがりになってしまう危険性があるからです。私もそんなきらいがあったことは否定できません……。とはいえ、学部レベルでは学問的な厳密さがそこまで求められるわけではありません。研究職を目指すわけでないのならなおさらです。それに、専門的な視点からのアドバイスが必要な場合は、ゼミを超えて、それを専門にしている先生のところに聞きに行けばよいのです。
「一から教えてください」だと嫌がられるのではないかと思われるかもしれませんが安心してください。もちろん、「ここまで調べたけれど、どうしてもわからない」という姿勢でのぞめば丁寧に教えてくれるでしょう。それができなくて「何から調べたらよいかわからない」場合も、「一から教えてください」ではなく、「何から調べたらよいのか」を聞けばよいのです。
新潟大学は、学生1人当たりの教員数でみれば、まだまだたくさんの教員がいるので、ゼミ以外の教員を利用しない手はありません。しかも、人文学部の場合は「サブゼミ」も履修するのが普通になっているので、そうしたことをするのにも恵まれた環境が整っています。
私も社会病理学の先生のもとで、フィールドワークから卒論を仕上げるに至るまで、さまざまな先生にお世話になりました。現代の社会問題を扱いたいからといって、社会学を専攻する必要はまったくありません。たとえば、言語文化専攻のゼミに入って、日本の社会問題を研究するのもありかと思います。そのゼミの教員から得られる海外の知見や海外からの視点は、相対化という点で、間違いなく自分の研究を豊かにしてくれるはずです(あくまで私見なので、そうしたい場合は、ゼミ希望を出す前に当該教員に相談してください!)。
そして、逆にいえば、社会学は社会問題だけを相手にしているわけではなく、世界のあらゆる事象をその研究対象にしています。主観的とされる人間の自我や自意識にはじまり、人間関係の悩みから客観的な科学法則に至るまで、一つひとつの事象がいかに「社会的」に(言い換えれば、さまざまな人や物のつながりによって)形成されているのか、そして人や物のつながりを組み直すことで、いかに変えていけるのかを問うのが社会学です。
大学院進学と留学と就職~人生で唯一、悩みのない時期
学生:へぇ~、参考になります! じゃあ社会病理学の先生のもとで地域社会学について学んだ後は大学院に進んだんですか?
伊藤先生:これもまたすごく悩んだところで、最初は公務員になろうと考えていたんです。それが大学進学時に交わした親との約束でもあったので。ただ、住民自治とか住民主体といっても、現実には、住民と一括りにできるような存在はいないわけです。それでも、そうした言葉が掲げられながら、行政が成り立っている。その「ごまかし」のように見えるものをどう扱っていけばよいのかがわからなくなり、もっと専門的に考えてみたいと思うようになりました。
学部4年の5月頃まで、公務員試験の勉強をしながら悩んでいたのですが、どうしても決めきれず、高専時代からお世話になっていた哲学の岡部先生に相談したところ、「自分がやりたいことがあるのなら、それをやった方がいい」とおっしゃっていただきました。それが決め手になって大学院で学びを深めることを決意しました。
親には、「約束と違う。お前が大学院に行っても、頭が良くないのだから、物になれるわけがない。金は出さんぞ!」と怒鳴られました。就職氷河期の時代にあって、確かに私は浮ついた存在だったので、私を試す思いがあったのかもしれません。それでも「自分で稼ぎながら行ってやる!」とあきらめなかったので、最後は何とか認めてくれました。
学生:そうだったんですね。これまでたくさん悩んできた先生ですが、大学院選びは大変ではなかったですか?
伊藤先生:あぁ それについては、まったく悩みませんでした。学部のゼミで、社会の「共同性」と「公共性」がいかにして生まれるかを特集した学術雑誌(日本社会学会の機関誌である『社会学評論』)を輪読した時に、地域社会を扱った論文を担当したところ、それが面白くて。大学院ではその先生(吉原直樹先生)のもとで研究したいと思ったんです。そこで、吉原先生に思い切ってメールを出したところ、名古屋での学会にいらっしゃるついでに会っていただいて、そして、吉原先生が在籍していた東北大学の大学院に進みました。
学生:なるほど、いい出会いがあったんですね。大学院では何を研究したんですか?
伊藤先生:私の理解では、地域社会学の基本的な視座のひとつは、地域社会の集合性(住民などと一括りにされるもの)は、自然にできあがるものではなく、「生活と支配」の両面から考えなければならないということです。
日本はもちろん、東アジアと東南アジアでも、中国で生まれたムラ単位での支配のシステムが広く行き渡っています(たとえば、徴税などもムラごとに行われたわけです)。今日でいえば、町内会や自治会と呼ばれる住民組織がそれにあたり、中国はもちろん、インドネシアやフィリピンでもみられるのですが、そうした組織は、他方では、住民同士の生活課題を共同で対処する単位でもあるわけです。そして、そうした生活の単位は、自然なものだから存続してきたわけではなく、支配の単位でもあったから存続している面もあるわけです。
今日でも、防災や防犯などさまざまな助け合いの場面で地域コミュニティの重要性が指摘されていますが、この歴史的経緯を踏まえると、「防災や防犯のために地域コミュニティを活用しよう」という掛け声は、支配(フーコー流に言えば統治)の手段にもなりえます。もちろん、私たちにとって何らかの秩序化は不可欠です。なにものにも囚われない自由は虚構に過ぎません。
しかし、それでも、外から与えられた「〇〇のために」が先行してしまい、そのために地域コミュニティがあるのだと発想してしまうと、その目的にそぐわないものは排除するという動きを生みだしかねません。戦時下の「銃後の守り」を思い起こしてください。
私が行ってきた「生活の共同」に関する研究から見えてきたのは、社会とは、ひとつの機能、目的、構造を前提とした人びとの集まりを指すのではなく、相異なる人びとが共生しあうことを可能にするために、互いに折り合いがついていく仕組みの集まりを指しているということです。このように他者と適切な距離を取るかたちで、地域の人びとは「上からの支配」も巧みに利用して、折り合いとしての「自己への配慮」(いくつもの「ひだ」の重ね合い)を行ってきたんです。
私はこのことを、日本の各地の地域社会で学ばせてもらいました。さらに、指導教員の吉原先生のおかげで、インドネシアのバリ島や中国のマカオでもフィールドワークを行い、国際比較研究へとつなげていくことができ、博士論文にまとめることができました。
いま考えてみると、こうした地域社会学の研究が、中学生の頃から経験してきた「枠にあてはめられることの窮屈さ」と「枠から逃れることの身勝手さ」との逡巡からの解放をもたらしてくれたのかもしれません。
大学院生時代は、とくに博士前期課程(修士課程)のときは本当にお金がなく、アルバイトを三つ掛け持ちして、月の食費も4,000円以内におさえていました。それでも、指導教員の吉原先生のおかげで研究は自由に好きなようにできていたので、人生で唯一、何の悩みもない時間を過ごせました。もちろん、学会発表や論文投稿がすべてうまくいっていたわけではなく、失敗することの方が多かったんですけど……。
ただ、5年かけて無事、博士課程を修了しても、就職先が用意されているわけではありません。当時は、大学院重点化で競争が激化していて、文系の場合、大学の正規のポストにつけたとしても平均で30歳代後半だと言われていました。
正規のポストにつくまでは、任期付きの有給の研究員のポストや非常勤講師の仕事があればまだよいのですが、そうでなければ、塾講師などのアルバイトを続けていかなければなりません。そのうえで、研究業績も積み重ねて、いろいろな大学の教員公募にアプライし続けなければならないんです。
私の場合は、みずほ銀行の留学奨学財団から奨学金を頂くことができたので、そのお金で、物価の安いマカオに留学して、生活と研究を成り立たせることにしました。
学生:留学ですか⁉ 大胆な決断ですね。
伊藤先生:あくまで生活と研究を成り立たせるための手段だったんですよ。2年間の予定でマカオに行って、その後は、有給の研究員で香港の大学に3年間行く計画を立てていましたが、マカオに移り住んで一年経った時に、山形大学の看護学科の先生(田中幸子先生)から連絡があり、「山形大学医学部でフィールドワークと統計ができる教員を求めているけれど、面接を受けてみないか」とおっしゃっていただきました。
なぜ、そんな連絡が私のところにきたのかと思いますよね。この先生とは大学院生時代に接点があって、当時、指導教員の吉原先生から「看護の先生と、看護師のセカンドキャリアについて一緒に研究してみないか」と誘われたんです。もちろん、私の研究関心に沿わないので断ってもよいのですが、「やれることはなんでもやってやろう」というのが私の精神でした。だから、自分のキャリアの役に立つかどうかは二の次で、共同研究をさせていただいたんです。でも、その経験があったから、就職の声がけを頂けることになった。本当に人生は何が役に立つのかわかりません。
山形大学の話は、医学部の医療政策学講座のポストだったので、やはり自分の専門とは違いましたが、「受けたいです!」って返事をして、一時帰国しました。ただ、面接は散々でした。初めて文系の人間を採用するということで、主だった診療科の教授が面接官で、1時間半にわたって「あなたの業績は?」「それは業績ではなく、ただの結果では?」「あなたの研究で世の中のなにがどう変わったのかを聞いているんだけど」といった具合で、心が折れないようにするだけで精一杯でした。
後で聞いたところ、各教授の先生方は採用に反対だったそうです。ところが、当時の医学部長(嘉山孝正先生)だけが「力不足だが、見どころはある。医療のことは自分が教える」と買って下さり、採用されることになりました。
大学教員生活~知らない世界に飛び込んでみる
その当時は、「医療崩壊」という言葉が喧伝されていて、「妊婦のたらいまわし」などといったかたちで医療現場がさまざまにバッシングされていました。しかし、「そうしたバッシングは、医療現場のことを十分に知らない人間が外から勝手なことを言っているだけだ。それに対抗するためには医療現場から正確な情報発信をしなければならない。医者は忙しいので、あなたに中に入ってもらい、現場がいかに限られた資源のなかで工夫して頑張っているのかを発信してほしい」というわけです。
そこで、山形中の病院を調査して回って、学術論文だけではなくマスメディアへの発信も行ったり、翌年からは、医学部長だった嘉山先生が国の審議会(診療報酬を決める中医協)の委員に選ばれて、山形と東京を2、3日ごとに往復する日々を過ごすことにもなったり、さらに翌年からは財務官僚だった村上正泰先生が講座の教授に着任されて、地方の現場と国の政策をつなぐ仕事に関わらせてもらうことにもなったりしました。
山形大学では10年間勤務して、いろいろな意味で筆舌に尽くしがたい経験をさせてもらいました。その後、家庭の事情で新潟に移住し、勤務先も妻が働いている新潟医療福祉大学に移りました。医療福祉大では、医学部での経験を活かして、医療情報管理学科というところで診療報酬請求事務や診療情報管理士の教育を行いました。山形での経験から、病院経営が悪化するなかで医療の質を確保するためにも、経営データと診療データを一体的に分析できる人材の育成が急務であると考えて、育成の現場に飛び込んでみたんです。
医療福祉大は本当に忙しい職場で、私がいろいろと手を出しすぎたせいでもあるのですが、一か月の勤務時間が教育と校務だけで300時間を超えてしまっており、その上で研究もしなければなりませんでした。医療福祉大は「面倒見のよい大学」を掲げ、留年率・退学率0%、資格試験合格率・就職率100%を目標にしているので、まともにやっているといくら時間があっても足りません。
しかし、私がそんな医療福祉大で目にしたのは、どんな世界にもそれぞれの全力で物事に取り組んでる人がいるということでした。大学教員は基本的に研究業績が評価や昇進の基準になるので、いくら教育や校務に打ち込んでも、まず日の目を見ることはありません。それでも、教育や校務に熱意を傾けている教員がいて、それに応える学生がいて、大学の実績を支えている姿を目にしたんです。
他方で「そうした教員は研究から逃げているだけだ」という声もありました。そこで、私は、教育や校務に熱心な教員を見習いつつも、片手間ではありましたが研究活動も続けていきました。
そんな医療福祉大で3年半務めた後、今年の4月から新潟大学でお世話になることになりました。大学院を出て15年経って、ようやく、自分の本来の専門について腰を据えて研究・教育できる環境になりました。
学生:地域社会の研究だけでなく多様な経験をされてきたんですね。今は新潟大学でどのような研究をしているんですか?
新潟大学での研究~アクターネットワーク理論について
伊藤先生:医学部に在籍しているときに同僚によく言われたのは「社会学は科学なのか? その考え方にエビデンスはあるの?」ということです。先ほども言いましたが、やはり他の分野からの視点は、自分を反省させてくれるきっかけになります。自分の社会学の方法を「科学的」にするとはどういうことなのか。その土台として私は「アクターネットワーク理論」に目を向けています。わかりやすく説明してみましょうか。
いまでこそアクターネットワーク理論は人文社会学のあらゆる分野に影響を及ぼしていますが、そもそもは「科学人類学」として始まりました。つまり、科学実験室での営みを、「外在する自然」といった私たちの近代的枠組みを抜きにして「近視眼的に」観察してみたのです。
そうすることで、科学という営みが、事物を連関させ(たとえば、実験室の環境)、その連関によって、世界に差異をもたらす存在を浮き彫りにして、さらに、実験室という特殊な環境でみられた存在を別の存在(データや文字や図表)に変換・移送させ、一般化させることで、その存在の実在性を高めていくものであることがわかりました。ちょっと難しいですよね。誤解のないように話そうとすると3時間ぐらいかかります……(来年度からGコード科目で「アクターネットワークの社会学」を開講して、私が翻訳した『社会的なものを組み直す―アクターネットワーク理論入門』を輪読するので、関心のある方はぜひ履修してください)。
このアクターネットワーク理論は、主体や客体、ミクロやマクロといった前提を外部から持ち込むことを認めません。そうすることで、世界の人や物が、どのようなかたちで人や事物を結びつけ、さらには、自らもまた人や事物のつながりのなかで形成されるなかで、科学に限らずさまざまな秩序がかたちづくられているのかが記述できます。これって、まさに地域社会学が焦点を当てようとしてきたことですよね。
ちなみに、アクターネットワーク理論もまた、私が高専時代から摂取してきた「経験的」な哲学との関連が強いんです。まさに、いろいろなものがつながって、アクターネットワーク理論に関心を向ける私自身が形成されていて、もっと正確に言えば、こんなふうにこれまでの来歴を物語ることを可能にしていて、だからこそ、アクターネットワーク理論ともつながることができたわけです。
ということで、現在は、アクターネットワーク理論の研究を深めるとともに、具体的なフィールドとして、主に高齢者の方の住宅環境に焦点を当てて、どのように人や事物を結びつけて、自らの生活や共同生活を成り立たせているのかといった研究や、医学部の救命救急医学分野の西山慶教授をはじめとする先生方にもご指導いただきながら、新潟県のドクターヘリの運航に関する研究も進めています。
学生に向けて一言~「やらなくてはいけないこと」に逃げない
学生:なるほど、社会の役に立つことがしたいという想いは今も変わっていないんですね。では、最後に先生の経験から学生に向けて一言お願いします!
伊藤先生:さきほど、つながりによって人が作られるという話をしましたが、ジンメルという社会学者は、つながりが増えるほど個性が生まれていくといっています。つまり、ひとつのつながりだけでは、「支配」や「模倣」や「縮小再生産」になってしまいますが、複数のつながりがあれば、いろいろな影響を受けて、ひとつに支配されることがなくなるということです。言い換えれば、いくつものつながりが「折り合って」、心のひだになっていくんです。しかも、私がそうであったように、さまざまなチャンスも舞い込んでくることもあります。
ですので、大学生活では、まずは、多くの「弱いつながり」をつくっていくことがよいのではないでしょうか。しかし、どのようなつながりでもよいわけではありません。自分の考えを押し付けてくるようなつながりは拒絶すべきです。他とつながる自由を奪うがゆえに、そうしたつながりから「他と異なるかけがえのない私」が作られることはないからです。だから、私の言っていることも、皆さんにとっては、いくつものつながりのなかのひとつにすぎません。
とはいえ、やたらといろいろとつながっていくのも、しんどいですよね。そこで、もう一方で、「確固たる私」を形作ってくれるような「分かちがたいつながり」を大切にすることも大事だと思います。「分かちがたいつながり」とは、分かりやすく言えば愛着のことです。愛着のある楽器だからこそ、自分らしい演奏ができるようになりますよね。推すことで、自分が推されていく。ただ受動的に消費しても、あるいは、やりたくないことをいくらやっても、「かけがえのない私」は作られません。
学問でもあるいはそれ以外でもよいと思うんですよ。さまざまな経験を積み重ね、知識を深めていくことで、自分がどうあってもやりたいものが見つかるはずです。それを探求してほしいです。大学生活は「やらなくてはいけないこと」だけに追われることがないからこそ、やりたいことが見つけられる好機であふれています。「やらなくてはいけないこと」に逃げてしまう、つまり、「やらなくてはいけないこと」だけで時間を埋めてしまうと、いつまでたっても「かけがえのない私」はできあがりません。
そして、限られたつながりを深めていく、つまりは、ある物事をとことん突き詰めて、かけがえのない自分自身を形作っていくなかで、今度は、その限界に気づき、それまでまったくつながっていなかったものにつながっていく契機も生まれていくのだと思います。
そうした姿勢こそが、大学で身に着けられる大切なことのひとつだと「私は」思っています。それは、今後、その時々の限られたつながりのなかで生きることが求められる職業生活を支えてくれるものになってくれるはずです。ただし、これはあくまでひとつの私見ですよ!
インタビューを終えて
考えること、行動することの大切さが感じられる濃いお話だったのではないでしょうか。地域社会の領域から飛び出して多くの経験をされてきた伊藤先生、先生のお話をもっと聞きたい方は 2 学期以降の授業を取ってみたり先生にメールを送ってみたり… 先生のように自分からアクションを起こしてみてはいかがでしょうか(齋藤)。
●伊藤嘉高(いとう ひろたか)先生
新潟大学人文学部・准教授
1980年2月生まれ、愛知県名古屋市出身
・専門:地域社会学、都市社会学、医療社会学
・所属:人文学部・社会文化学プログラム、大学院・現代社会文化研究科
・研究室ウェブサイト(ブログ)
・学部ゼミページ